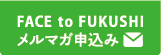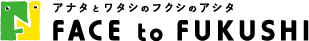サービス管理責任者
サービス管理責任者
【略称】サビ管

障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスを実施する事業所および指定障害者支援施設において、個々のサービス利用者の初期状態の把握や個別支援計画の作成、定期的な評価など一連のサービス提供プロセス全般に関する責任や、他のサービス提供職員に対する指導的役割を担う職員。主に療養介護、生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、共同生活援助、共同生活介護、就労移行支援、就労継続支援、施設入所支援を行う場合に配置される。
 サービス提供責任者
サービス提供責任者
【略称】サ責、サー提

訪問介護(ホームヘルプサービス)事業所の柱となる役職。利用者宅に出向き、サービス利用についての契約のほか、アセスメントを行い必要な訪問介護計画の内容についての話し合いなどを行う。また、実際のサービス内容に関して訪問介護員(ホームヘルパー)への指導・助言・能力開発等の業務も行う。
 在宅介護
在宅介護

障害や老化のために生活を自立して行うことができない人が、自分の生活の場である家庭において介護を受けること。またはその人に対して家庭で介護を提供すること。家庭は利用者の持つ多面的なニードに対応しやすく、ノーマライゼーションの観点からも重要な介護の場である。
 3K
3K

「きつい (Kitsui) 」「汚い (Kitanai) 」「危険 (Kiken) 」のこと。
介護・福祉業界の労働環境を揶揄して使われることがある。
 支援費制度
支援費制度

身体障害者(児)及び知的障害者(児)が、その必要に応じて市町村から各種の情報提供や適切なサービス選択の為の相談支援を受け、利用するサービスの種類ごとに支援費の支給を受け、事業者との契約に基づいてサービスを利用できる制度。2003年(平成15年)4月に施行され、2006年(平成18年)4月に障害者自立支援法へ移行した。
 四肢麻痺
四肢麻痺

両上肢、両下肢に運動麻痺が起こった状態のこと。脳障害や脊椎損傷などが原因となり起こる場合が多い。
 自閉症
自閉症

社会性の障害や他者とのコミュニケーション能力に障害・困難が生じたり、こだわりが強くなる精神障害の一種。先天性の脳機能障害とされるが、脳機能上の異常から認知障害の発症へといたる具体的なメカニズムについては未解明の部分が多い。
一般的には、発達障害の一種である自閉症スペクトラムのうち、いわゆる従来型自閉症と呼ばれるもの(あるいはスペクトラムピラミッドの頂点に近いところに位置している状態)を、単に「自閉症」と称することが多い。
 自閉症スペクトラム
自閉症スペクトラム

自閉症、特定不能の広汎性発達障害などの各疾患を広汎性発達障害の連続体の1要素として捉えたもののことである。自閉症連続体(じへいしょうれんぞくたい)、自閉症スペクトル(じへいしょうスペクトル)などともいう。
 社会起業家
社会起業家

社会変革の担い手として、社会の課題を、事業により解決する人のことを言う。社会問題を認識し、社会変革を起こすために、ベンチャー企業を創造、組織化、経営するために、起業という手法を採るものを指す。
 社会福祉協議会
社会福祉協議会
【略称】社協

社会福祉法の規定に基づき組織される地域福祉の推進を目的とする団体で、単に「社協」とも呼ばれる。市区町村を単位とする市区町村社会福祉協議会、指定都市の区を単位とする地区社会福祉協議会、都道府県を単位とする都道府県社会福祉協議会がある。社会福祉を目的とする事業を経営する者および社会福祉に関する活動を行う者が参加するものとされており、さまざまな福祉サービスや相談、ボランティア活動や市民活動の支援、共同募金など地域の福祉の向上に取り組んでいる。
 社会福祉士
社会福祉士
【略称】社福士(シャフクシ)

社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、国家試験に合格し厚生労働大臣の免許を受けた者。社会福祉の専門的知識および技術をもって、身体上もしくは精神上の障害があること、または環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者、または医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連絡および調整その他の援助を行う専門職である。介護保険制度においては、包括的支援事業を適切に実施するため地域包括支援センターに配置されている。
 社会福祉法人
社会福祉法人
【略称】社福(シャフク)

社会福祉事業を行うことを目的として社会福祉法に基づいて設立された法人をいう。社会福祉法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律や公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に規定される公益法人よりも、設立要件を厳しくしており、公益性が極めて高い法人であるといえる。このため、自主的な事業経営の基盤強化、透明性の確保、提供するサービスの質の向上といった観点が求められる一方、税制上の優遇措置などがとられるといった特徴がある。
 社会保障審議会
社会保障審議会
【略称】社保審(シャホシン)

厚生労働大臣の諮問機関。厚生労働省設置法(平成11年法律97号)に基づいて厚生労働省内に設置された審議会の一つ。厚労相や関係各大臣の諮問に応じて社会保障制度や人口問題に関する重要事項について調査・審議し,厚労相や関係行政機関に意見を述べる。
 障害者総合支援法
障害者総合支援法

障害者自立支援法が一部改正され、平成25年4月から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律として、「障害者総合支援法」と名称が変更された。
障害者の定義に難病等が加わり、障害者の範囲が変更されたり、障害程度区分から障害支援区分に変更されたりしている。
 生活困窮者
生活困窮者
【略称】生困者(セイコンシャ)

収入がなく生活に困っている人を指す語。多くの場合、生活保護法などにより扶助の対象となる人を指す。
 生活困窮者自立支援法
生活困窮者自立支援法
【略称】生困法(セイコンホウ)

経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある人に対して、自立の促進を図るための措置を講ずることを定めた法律。就労など自立に関する相談や、住居の確保に必要な費用の給付などを行う。平成25年(2013)公布。平成27年(2015)4月施行。
 生活の質
生活の質

一般的な考えは、生活者の満足感・安定感・幸福感を規定している諸要因の質。諸要因の一方に生活者自身の意識構造、もう一方に生活の場の諸環境があると考えられる。この両空間のバランスや調和のある状態を質的に高めて充足した生活を求めようということ。この理念は、医療、福祉、工学その他の諸科学が、自らの科学上・技術上の問題の見直しをする契機になった。社会福祉および介護従事者の「生活の場」での援助も、生活を整えることで暮らしの質をよりよいものにするという生活の質の視点をもつことによって、よりよい援助を求めることができる。QOLとも呼ばれる。
 精神保健福祉士
精神保健福祉士
【略称】PSW(ピーエスダブリュー)、PS(ピーエス)

精神病院や社会復帰施設、および保健所などに勤務して、精神科の患者に対し、社会復帰のための手助けする仕事をする。また家族の相談相手になったり、医師や看護婦、作業療法士などの治療チームの調整役を務めるなどさまざまな役割を持っている。精神障害者の福祉向上のためにニーズが高まっている職業。
社会福祉士、介護福祉士と並ぶ福祉の国家資格(通称:三福祉士)のひとつ。
精神保健福祉士法(1998年)に基づき、精神障害者の保健や福祉に関する専門的知識と技術を持ち、社会復帰への相談援助を行う者として位置付けられた国家資格。精神医学ソーシャルワーカーもしくは、精神科ソーシャルワーカー(PSW)とも呼称される。
 全国社会福祉協議会
全国社会福祉協議会
【略称】 全社協(ゼンシャキョウ)

社会福祉協議会の全国組織。社会福祉法における「社会福祉協議会連合会」にあたる。国の機関(厚生労働省等)との協議、各社会福祉協議会との連絡・調整、福祉に関する調査・研究、出版等の活動を行っている。一般的には、「全社協」の略称で呼ばれる場合が多い。
 ソーシャルワーカー
ソーシャルワーカー
【略称】SW

一般的には社会福祉従事者の総称として使われることが多いが、福祉倫理に基づき、専門的な知識・技術を有して社会福祉援助を行う専門職を指すこともある。
医療ソーシャルワーカー(MSW)、コミュニティソーシャルワーカー(CSW)、スクールソーシャルワーカー(SSW)など活動する場面によっていろいろな呼び名がある。