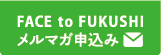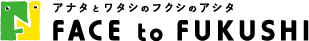介護給付
介護給付

要介護認定を受けた被保険者に対する保険給付。原則、支給限度基準額の9割が保険給付され、残りの1割が利用者の自己負担となる。また、労働者災害補償保険法に基づく保険給付の一種として介護給付がある。
 介護支援専門員【ケアマネジャー】
介護支援専門員【ケアマネジャー】

介護保険制度で、要介護者又は要支援者からの相談に応じるとともに、要介護者等がその心身の状況等に応じ適切なサービスを利用できるよう、市町村、サービス事業者、施設などとの連絡調整等を行う人のこと。
 介護職員初任者研修
介護職員初任者研修

平成25年4月より、「訪問介護員養成研修(1級~3級)」(いわゆるホームヘルパー1級〜3級)及び「介護職員基礎研修」は「介護職員初任者研修」に一元化された。本研修は、訪問介護事業に従事しようとする者、もしくは在宅・施設を問わず、介護の業務に従事しようとする者が対象となります。
 介護の日
介護の日

介護についての理解と認識を深め、介護サービス利用者およびその家族、介護従事者等を支援するとともに、これらの人たちを取り巻く地域社会における支え合いや交流を促進する観点から、高齢者や障害者等に対する介護に関し、国民への啓発を重点的に実施する日。日にちは11月11日。
 介護福祉士
介護福祉士
【略称】介福(カイフク)

社会福祉士及び介護福祉士法によって創設されたケアワーク専門職の国家資格。介護福祉士の登録を受け、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上または精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者に心身の状況に応じた介護(2015(平成27)年度からは喀痰吸引等を含む)を行い、並びにその者およびその介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とする者をいう。資格取得のためには、介護福祉士養成施設を卒業するか介護福祉士国家試験等の合格が必要となる(2015(平成27)年度からは養成施設卒業者も国家試験合格が必要)
 介護報酬
介護報酬

介護保険制度において、サービス提供事業者や介護保険施設が介護サービスを提供した場合や、居宅介護支援事業者が居宅介護支援(介護サービス計画の作成等)を行った場合等にその対価として支払われる報酬。その基準額については、厚生労働大臣が定める。原則として利用者はその1割を自己負担し、残りの9割については保険者から事業者に支払われる。
 介護保険
介護保険

主として、加齢に伴い介護を要する状態に陥ることを保険事故とする保険制度の総称。介護保険法でいう介護保険とは、被保険者の要介護状態や要支援状態に関して必要な保険給付を行う。
 介護保険法
介護保険法

介護が必要になった方に保健医療サービスや福祉サービスに関する給付を行うために、1997年(平成9年)12月17日に公布、2000年(平成12年)4月1日に施行された法律。
介護する家族の負担を軽減し、社会全体で介護を支える新しい仕組みとして誕生した介護保険制度について定められた。
 介護予防サービス
介護予防サービス

介護予防サービスとは、要介護状態になることをできるだけ防ぐとともに、要支援状態になっても状態の悪化を防ぐことに重点をおいたサービス。介護予防サービスを受けることができる人は、要支援認定で「要支援1」「要支援2」に認定された人。介護予防サービスは、市区町村の地域包括支援センターが中心となって支援する。サービスを利用するためには、まず、地域包括支援センターに相談し、「介護予防ケアプラン」の作成を依頼し、そのプランに沿ってサービスを利用する。
 ガイドヘルパー【移動介護従業者】
ガイドヘルパー【移動介護従業者】

単独で外出することが困難な方への歩行や車いすの介助、外出先での食事の介護などを行う。ガイドヘルパーの利用料は自治体によって異なる。
移動介護従業者、移動支援従事者、外出介助員とも呼ばれる
 学習障害(LD)
学習障害(LD)

全般的な知能の水準や身体機能に障害は見られないが,読み書き・計算や注意の集中といった能力に欠けるために学習が困難な状態。ラーニング-ディスアビリティー。 LD。
 片麻痺
片麻痺

身体の右片側または左片側に神経の麻痺のある場合をいう。麻痺側の反対の脳の血管障害や外傷(脊髄にも生じ得る)によって起こることが多い(脳性片麻痺)。運動麻痺、知覚麻痺のいずれか、または両方の麻痺の場合がある。
 下半身麻痺
下半身麻痺

下半身の運動と知覚をつかさどる神経の障害によって生ずる麻痺。主に脊髄損傷の人に起こるが、脳性麻痺の人にもみられることがある。車いすが移動手段となり、排尿・排便のコントロール障害が生じ、褥瘡に罹患しやすい。男性の場合には性的機能に不安をもつこともある。
 グループホーム
グループホーム
【略称】グルホ

認知症高齢者や障害者等が、住み慣れた環境で、自立した生活を継続できるように、少人数で共同生活を営む住居またはその形態である。これらの居住者に対する日常生活援助等のサービスを指す意味でも用いられる。介護保険法および障害者総合支援法において、給付対象サービスとして位置づけられている。
 ケアプラン
ケアプラン

個々人のニーズに合わせた適切な保健・医療・福祉サービスが提供されるように、ケアマネジャー(介護支援専門員)を中心に作成される介護計画のこと。ケアプランは、①利用者のニーズの把握、②援助目標の明確化、③具体的なサービスの種類と役割分担の決定、といった段階を経て作成され、公的なサービスだけでなく、インフォーマルな社会資源をも活用して作成される。
 ケアマネジメント
ケアマネジメント

生活困難な状態になり援助を必要とする利用者が、迅速かつ効果的に、必要とされるすべての保健・医療・福祉サービスを受けられるように調整することを目的とした援助展開の方法。利用者と社会資源の結び付けや、関係機関・施設との連携において、この手法が取り入れられている。介護保険においては、ケアマネジメントは「居宅介護支援」と呼ばれる。
 ケアマネジャー【介護支援専門員】
ケアマネジャー【介護支援専門員】
【略称】ケアマネ

介護保険制度で、要介護者又は要支援者からの相談に応じるとともに、要介護者等がその心身の状況等に応じ適切なサービスを利用できるよう、市町村、サービス事業者、施設などとの連絡調整等を行う人のこと。
 ケースワーカー
ケースワーカー

地域で福祉サービスを必要としている人の相談に乗り、保育所などの福祉施設の入所や生活保護を必要とする人への適用手続きをする人で、市町村役所の福祉課や、児童相談所、保健所、病院や福祉施設などで働いている。
各地方自治体の福祉事務所で社会福祉士として勤務する公務員のことをケースワーカーと呼ぶ。この仕事に就くには、大学、短大、専門学校などで社会福祉系の専門コースを履修し、社会福祉主事任用資格を取得した後、地方公務員試験を受験する。
 ケースワーク
ケースワーク

困難な課題、問題をもった対象者が主体的に生活できるように支援、援助していく個人や家族といった個別に対するソーシャルワーク(社会福祉援助技術)のことである。
元来は英語で、日本語では個別援助技術(こべつえんじょぎじゅつ)と翻訳され、専門書でも実際にそのように表記されるが、指導・ディスカッション等の福祉における現場では「ケースワーク」の呼称の方が一般化している。
 権利擁護
権利擁護

自己の権利や援助のニーズを表明することの困難な障害者等に代わって、援助者が代理としてその権利やニーズ獲得を行うことをいう。